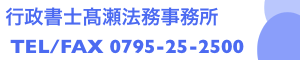相続放棄とは
相続放棄するとはじめから相続人でなかったことになります。自分が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に被相続人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に申し出なければなりません。家庭裁判所で伸述を貰い簡単な事項を記入すればひとりでできますが、相続人全員でそろって提出してくださいと言われることが多いようです。
限定相続とは
相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、相続人の財産を持ち出してまでは弁済しないという制度。相続人であることを本人が知った日より3ヶ月以内に行う。
遺留分(いりゅうぶん)とは
相続人に留保された、相続財産の一定の割合 のことをいいます。遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。そこで法は遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言者が遺言で指定する場合や、 利害関係人の申立てによって家庭裁判所で選任される場合があります。 遺言執行者がいると、相続人であっても遺言の執行を妨害できません。
遺 贈 (いぞう)
遺言で、遺産の全部または一部を譲与することができます。 遺言でしなければならない点で、譲与される相手との契約ではありません。 これが契約の場合は、死因贈与がありますが、 贈与する人と贈与される人との死因贈与契約です。
「全文が自署により書かれている」こと「日付と氏名の記載」「印鑑」が必要とされ(民法968条)この内一つでも不備があれば遺言書は無効となってしまいます
相続人の権利を奪う遺留分侵害を内容にしたもの
公序良俗に反するような内容は無効となります
誰に何を(どの財産を)相続させるかが不明瞭な場合
代襲相続(たいしゅうそうぞく)
推定相続人(現状のままで相続が開始された場合に相続人になることができる人)、 例えば、被相続人の子または兄弟姉妹が、被相続人の死亡以前に死亡していた場合、 相続人の廃除、相続欠格によって相続権を失ったときは、 被相続人の子のこの子(孫)または兄弟姉妹の子が、代わって相続します。 このことを代襲相続といいます。 相続放棄した人は、相続開始前に相続権を失ったとはいえないので、 代襲相続は認められません。
相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分によることはありません。
単純承認
単純証人とは、相続人が、被相続人の権利義務を無条件に承継することをいいます。 被相続人の債務も当然承継します。
廃除
あいつには遺産をやりたくない」という場合、被相続人の意思で相続権を奪う制度です。遺留分をもつ推定相続人(相続人になる予定の人)が被相続人に対し虐待や侮蔑をした時や、推定相続人に著しい非行がある場合、家庭裁判所に廃除を請求できます。廃除は遺言で示すこともできます。
特別受益
複数の相続人の間で公平を図る制度です。一部の相続人が被相続人の生前に財産をもらっていた場合、その額を考慮して分配します。
寄与分
これも相続人の間で公平を図る制度です。一部の相続人が、被相続人の仕事を長く手伝ったりりして、財産の維持や増加に寄与した場合、その働きを寄与分として考慮します。
遺産分割
相続人が複数いる場合は、相続財産は、相続開始と同時に共同相続人の共有になります。この共有の状態はあくまで仮の状態ですから、各相続人に何を、どのように分配するかを具体的に決めなければなりません。この分配するための手続きを遺産分割 といいます。
相続のページに戻る